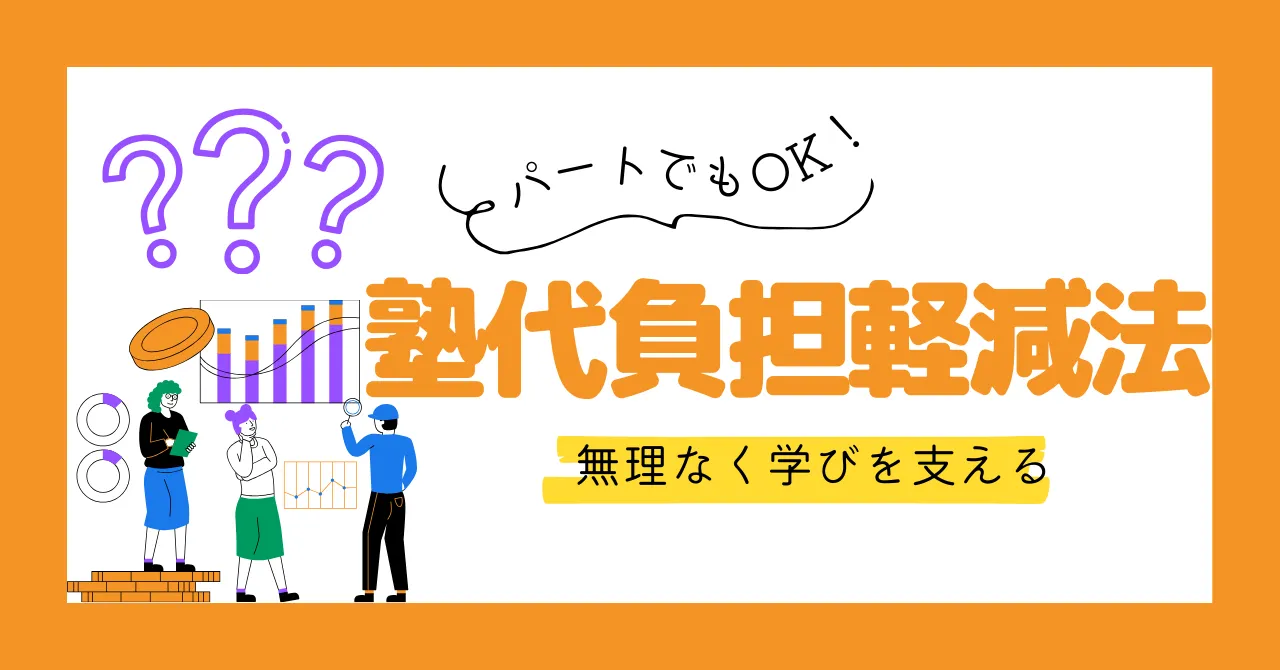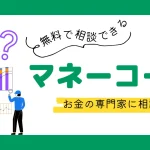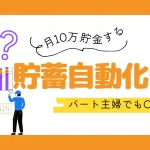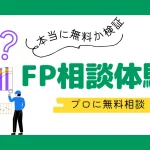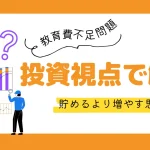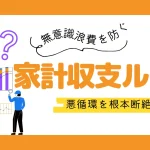子どもの将来のために塾に通わせたい──でも、パート収入だけでは毎月の塾代で家計がギリギリ。
「せっかく働いても、塾代でほとんど消えてしまう…」そんな現実に、頭を抱えている主婦は少なくありません。
実は、多くの家庭がちょっとした工夫と情報の差で、塾代の負担を大幅に軽くできることをご存知でしょうか?
本記事では、塾代に悩むパート主婦が「無理なく、安心して子どもの学びを支える」ための以下の具体策をすべて公開します。
読み進めれば、今まで“家計の悩み”と思っていた塾代が、実は“計画的にコントロールできるお金”に変わることがわかるはずです。
あなたも、今日から家計の不安を減らしながら、子どもの未来に投資できる方法を手に入れませんか?
Contents
塾代が家計を圧迫…パートで働く主婦が抱えるリアルな悩み
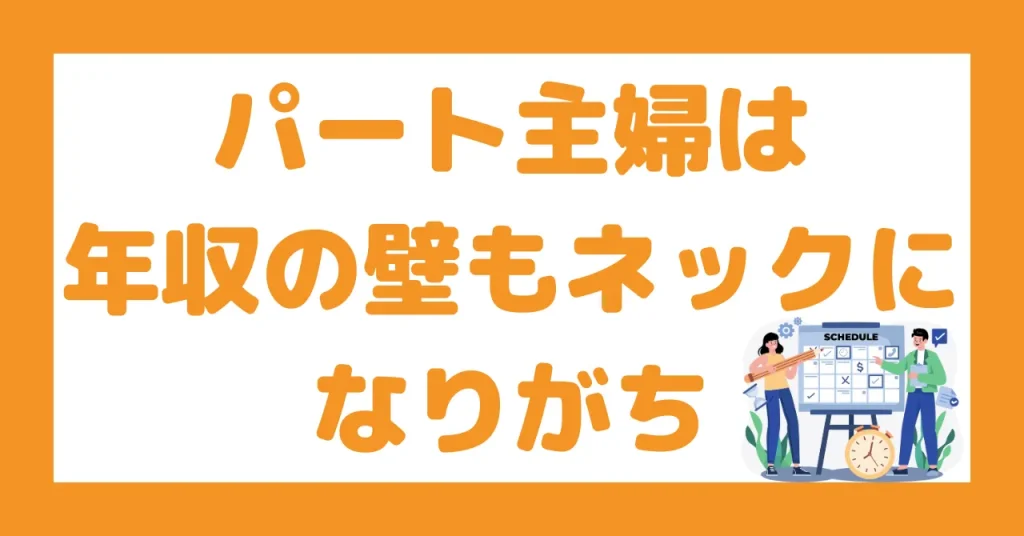
文部科学省や各教育機関の調査によると、子ども1人あたりの塾代は年間で平均20〜40万円。受験期になると100万円以上に達するケースもあります。
ここでは、「なぜ働いても余裕が出ないのか」、そして「どうすれば塾代を無理なくまかなえるのか」を明らかにしていきます。
「塾代でパート代が消える」主婦の現実とは
「子どもの教育費を支えたい」そう思って始めたパートなのに、給料明細を見るたびにため息が出る——。
例えば、時給1,100円で週4日・5時間働くと、月収は約8万8,000円。ところが塾代が月3〜5万円かかれば、手取りの半分以上が教育費で消えてしまいます。
加えて、交通費・昼食代・被服費・税金などの支出もあるため、実際に家計に残るお金はごくわずかです。
さらに、学校行事や子どもの体調不良で勤務日数が減ると、予定していた収入が減少。
「塾代を払うために働いているのに、そのために自分の時間もお金も奪われている」——そんな“堂々巡り”に悩む主婦は多いのです。
このような状況が続くと、精神的にも追い込まれることに。
「塾をやめさせるべきか」「子どものために我慢すべきか」、といった葛藤に直面します。
教育費の増加とともに苦しくなる家計のバランス
教育費は、家計を圧迫する“見えにくい固定費”です。
特に中学・高校に進むにつれ、塾代・模試代・教材費などが雪だるま式に増加します。
総務省の家計調査によると、子ども1人の教育費は、
- 小学生:約12万円/年
- 中学生:約30万円/年
- 高校生:約45万円/年
と年齢に応じて増加。
一方で、パート主婦の平均年収は約120万円前後。教育費が家計全体の20〜30%を占めるケースも珍しくありません。
このため、「食費を削る」「レジャーを我慢する」「自分の医療費を後回しにする」など、生活の質を落とさざるを得ない家庭も多いのです。
また、物価上昇やエネルギー費高騰の影響で、教育費以外の出費も増加傾向に。
結果として塾代が家計を圧迫し、“パート代では追いつかない”という状態に陥りやすくなってしまいます。
扶養の壁・社会保険・税金…“働き損”になりやすい落とし穴
パート主婦が塾代をまかなうために勤務時間を増やそうとすると、次にぶつかるのが「扶養の壁」です。
たとえば、
- 103万円の壁:所得税が発生
- 106万円の壁:社会保険の加入義務(勤務先による)
- 130万円の壁:夫の扶養から外れる
これらを超えると手取りが一気に減り、「働いた分だけ損をする」状態になりがちに。
「あと少し稼ぎたいのに、税金と保険で手取りが減る」——この“働き損ゾーン”こそ、多くのパート主婦が塾代捻出で苦しむ最大の理由です。
さらに、社会保険に加入すると保険料負担が増えるだけでなく、夫の家族手当がカットされるケースもあります。
結果的に家計全体で見れば収入が増えない、またはマイナスになることも。
つまり、「塾代を払うためにパートを増やす」という単純な解決策が通用しないのです。
この落とし穴を回避するには、税・社会保険・家計バランスをトータルで考える視点が欠かせません。
▼パート収入でも無理なく貯める方法はこちらの記事が役立ちます。
パート収入と塾代の関係を数字で見る:どれくらい負担している?

教育費は“見えない固定費”になりやすく、知らないうちに家計を圧迫していることも。
ここでは、最新のデータをもとに「塾代の平均額」と「パート収入とのバランス」を数値で可視化し、どこからが無理のあるラインなのかを整理していきます。
小・中・高校別に見る塾代の平均額と家計への影響
文部科学省「子供の学習費調査(2023年)」によると、学校種別の塾代(いわゆる「補助学習費」)の平均額は以下の通りです。
| 学年 | 公立の場合 | 私立の場合 |
|---|---|---|
| 小学生 | 約7万4,000円/年 | 約29万7,000円/年 |
| 中学生 | 約28万1,000円/年 | 約43万5,000円/年 |
| 高校生 | 約18万7,000円/年 | 約23万9,000円/年 |
特に中学生の時期に塾代が急増し、年間で約30万円前後(私立なら40万円以上)かかるのが一般的。これは月あたりに換算すると、2万5,000〜3万5,000円程度です。
もし子どもが2人いれば、単純計算で月7万円近い出費にもなります。たとえパートで月10万円ほど稼いでいても、その7割が塾代で消える計算に。
つまり、多くの主婦が感じている「塾代でパート代が消える」という感覚は、感情ではなくデータで見ても明確な現実なのです。
主婦の平均パート収入と塾代の割合:どこに無理がある?
厚生労働省「賃金構造基本統計調査(2024年)」によると、女性パートの平均時給は約1,200円で、週4日・1日5時間勤務とすると月収は約9万6,000円(年収約115万円)です。
このうち、もし塾代が3万円なら収入の約3割。2人分なら6万円で、収入の6割が教育費に消えます。
さらに、ここに食費・光熱費・住宅ローンなどの固定費が加わると、当然家計は赤字に傾くことに。
しかも塾代は季節講習(春・夏・冬)で、一時的に月10万円以上かかることもあります。
つまりパート代だけで塾代をまかなうのは、現実的にはかなり厳しい構造です。
この「収入と支出のギャップ」を理解しておくことが、家計破綻を防ぐ第一歩といえます。
塾代の家計圧迫を防ぐために知っておきたい現実的なライン
塾代にどれだけお金をかけるのが“無理のない範囲”なのかは、明確な基準があります。
家計の専門家によると、教育費(塾・教材・学校関連費など)に充てる理想的な割合は手取り月収の10〜15%。
つまり、パート収入が月10万円なら塾代の上限は1万〜1万5,000円が目安です。
これを超えると、生活費や貯蓄を削ることになり、長期的には家計が破綻しやすくなります。
また、「家計の収支は黒字でも、心理的に圧迫感がある」場合も要注意。
特に教育費は“支出の優先順位”が高いため、他の出費を犠牲にしてでも払い続ける傾向があり、結果的にバランスを崩しやすいのです。
無理を防ぐ具体策
- 塾代の年間総額を把握し、「講習込みの年間予算」を決める
- 教科を絞って「成果の出やすい科目」に集中する
- 通信教育・家庭教師など費用対効果の高い代替手段を検討する
「頑張って働く前に、“どこまでなら無理なく払えるか”を見直す」ことが、家計圧迫を防ぐ鍵です。
データから見える“教育費のピーク”と備えの必要性
教育費には、「中学3年〜高校3年の時期」の避けて通れない“ピーク”が存在します。
この6年間で塾代・受験費用・入学金などが集中し、1人あたり合計200〜300万円が必要になるとも言われることも。
高校・大学受験が重なる家庭では、一時的に年100万円以上の教育費負担になることもあるのです。
そのため、「今がギリギリでも、なんとかなる」と考えるのは危険。今後数年の見通しを立て、“教育費の波”を前もってシミュレーションすることが欠かせません。
教育費のピークに備える3つの行動を、確認しておきましょう。
| ①教育費専用口座をつくる | 塾代・教材費などを明確に分け、月ごとに積み立てておく。 |
| ②ボーナス・児童手当を教育費に充てる | 急な出費に備え、定期的な資金確保を意識。 |
| ③「学習投資の見直し」を年1回行う | 成果の出ない科目・塾・講師を惰性で続けない。 費用対効果を可視化する。 |
塾代は「子どもの将来への投資」である一方で、無理な支出は家計を長期的に圧迫します。
パート主婦が安定して教育費をまかなうには、感情ではなく数字で家計を把握する習慣が大切です。
▼家計や教育費の不安は専門家に相談するのが一番の解説策です。
パート主婦が“働き損”にならずに塾代をまかなう働き方
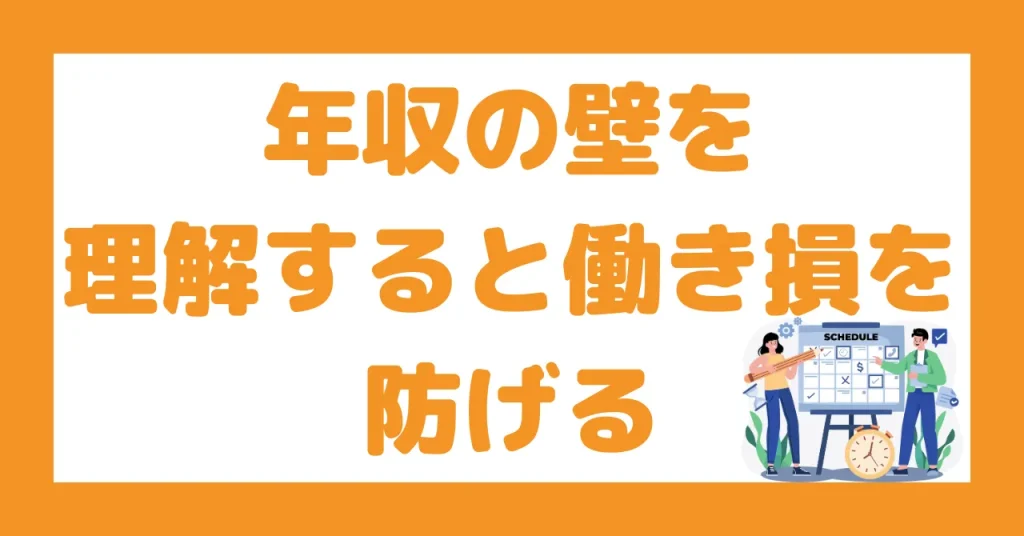
パート主婦には「扶養の壁」があるため、知らずに働きすぎると逆に損するケースも。
ここからは、パート内で”働き損”にならないための基礎知識や、効率の良い働き方を深堀していきます。
扶養範囲別シミュレーション:103万・130万・150万円の壁を理解
塾代を払うためにパート時間を増やしたら、「手取りが減ってしまった」という声は少なくありません。
その原因が、いわゆる「扶養の壁」です。
一般的に、
- 103万円の壁:所得税の扶養控除が外れる
- 130万円の壁:社会保険の加入義務が発生する
- 150万円の壁:配偶者特別控除の減額が始まる
ラインを指します。
具体的には、年収130万円を超えると健康保険や年金に加入する必要があり、年間20〜25万円ほどの負担が増えるケースも。
つまり、働く時間を増やしても、手取りがほとんど増えない「働き損ゾーン」に突入するリスクがあるのです。
塾代をまかなう目的で働くなら、まずは自分の家庭がどの「壁」の影響を受けるのかを把握し、「手取りでいくら残るか」から逆算して働き方を考えることが重要です。
塾代を目的に働くなら「時給」「勤務日数」「控除」のバランスがカギ
「あと2万円あれば塾代が払える」という理由で、勤務時間を延ばす主婦も多いですが、時給や控除を考慮しないと損をするケースもあります。
時給1,100円で月90時間働けば約9.9万円、年間で約118万円となり、103万円を超えるため所得税がかかるためです。
このとき、配偶者控除の対象外になっても、勤務日数を減らして別の収入源を組み合わせるなどの工夫で、手取りをキープできます。
また、「交通費非課税枠」や「社会保険の加入条件」などをうまく利用することで、扶養内ギリギリまで働きながら塾代を確保する方法も。
つまり、塾代を目的とした働き方では、「いくら稼ぐか」よりも「どの条件で働くか」のほうが大切です。
扶養を外すか迷ったときに確認すべき「手取りと支出の見直しポイント」
「もう少し稼いで塾代に充てたいけれど、扶養を外すと損かも…」と迷う主婦は多いです。
この場合は、まず「社会保険料の増加」と「手取りの増加額」を比較しましょう。
たとえば、年収150万円で社会保険加入となった場合、保険料や税金を引いた手取りはおよそ120万円前後。
一方、扶養内で働いた場合の手取りは約100万円前後なので、実質的には年間20万円のプラス。
ここに通勤費や昼食代などの実費を差し引くと、思ったより差がないケースもあります。
そのため、「扶養を外して働く=得をする」とは限らず、支出の見直し(通信費・サブスク・保険料など)とセットで判断することが賢明です。
在宅ワーク・スキル系副業など“第二の収入源”も選択肢に
塾代をまかなうための手段は、パートだけではありません。
近年では、主婦が在宅でできる副業やスキルワークを活用し、扶養範囲内で収入を増やすケースが増えています。
たとえば、
- ライティング・データ入力などの在宅ワーク
- ハンドメイドやフリマ販売
- ブログ・アフィリエイト・SNS収益
- オンライン講師・家計相談などのスキル副業
これらは、通勤時間ゼロ・家事の合間にできる点がメリットです。
特に「子どもの勉強時間に合わせて働ける」点は、塾代を目的とする主婦にとって大きな利点。
ただし、副業収入も年間の所得に含まれるため、税金・扶養の範囲を意識しながら管理することが大切です。
長期的には、こうしたスキル系副業を育てることで、子どもの教育費ピーク期(中高生〜大学生)に備えることもできます。
▼教育費が足りないときの具体的な対策はここから確認できます。
塾代の家計圧迫を防ぐ!教育費を上手にコントロールする方法

「あの有名な塾に通わせておけば安心」「とりあえず勧められたカリキュラムで続けている」そんな人は、一度利用内容を見直すことで家計の圧迫を防げるケースも。
ここからは、学習内容の見直し方法や成果を落とさずにコストカットする方法を解説します。
塾費用を抑える3つの見直し(通塾回数・教科数・講習費)
塾代が家計を圧迫していると感じたら、まず見直すべきは「塾の利用内容」です。
多くの家庭では、成績アップを願うあまり「必要以上の受講」をしているケースも少なくありません。
| ①通塾回数の見直し | ・週3〜4回→2回に減らすだけで年間10万円以上の節約につながる ・小学生のうちは家庭学習で補える教科も多く、回数を減らしても十分成果が出せる |
| ②教科数の見直し | ・苦手教科だけをピンポイントで受講する方法もあり ・数/英は塾・他の教科は通信教材や家庭学習でカバー→費用を3分の2程度に抑えられる |
| ③講習費の見直し | ・夏期/冬期講習は高額になりがち ・単発受講を検討してみる |
「塾=すべて受けなければならない」という固定観念を外すことで、無理のない支払い計画を立てられます。
公的支援や助成金を活用して塾代を軽減する方法
意外と知られていませんが、塾代の一部をサポートしてくれる公的制度があります。
自治体によっては、「子育て支援」「学習支援事業」「就学援助制度」などの名目で塾費用を補助してくれるケースも。
| ①就学援助金 | ・低所得世帯向け ・学用品費や学習補助費が支給される |
| ②子どもの学習支援事業 | ・ひとり親家庭向け ・無料または格安で塾に通える |
| ③学習支援教室 | ・地域ボランティア主導 ・無料学習会や教材配布 |
また、塾によっては兄弟割引・母子家庭割引・長期通塾割引などの制度を設けているところもあります。
「申請しなければ受けられない支援」も多いため、自治体の公式サイトで一度確認しておくとよいでしょう。
通信教材・家庭学習との併用で成果を落とさずコストカット
「塾を減らしたら成績が下がるのでは…」という不安を抱く親御さんも多いですが、今は通信教材や家庭学習ツールの質が格段に向上しています。
例えば、Z会・進研ゼミ・スタディサプリなどは、月3,000〜6,000円ほどでプロ講師の授業や添削指導が受けられます。
さらに、タブレット教材を活用すれば「通塾時間」や「交通費」も削減できるため、経済的にも時間的にも効率が良い学び方が可能です。
また、「塾+通信教材の併用」で苦手分野は家庭で補強し、塾は得意分野の強化に集中するなど、学習効果を高めながら費用を抑える戦略も有効。
家庭での声かけや進捗管理を習慣化すれば、子どもの自立学習力も育ちます。
家計簿で“塾代の固定費化”を防ぐ具体的な管理術
塾代は「教育投資」という名目で支払い続けてしまいがちですが、家計簿上では“固定費”として膨らみ続けるリスクがあります。
家計圧迫を防ぐには、塾代を「毎月の固定支出」ではなく、「期間限定の教育費」として管理することがポイントです。
具体的な、3つの管理術を確認しておきましょう。
- 塾代専用口座を作る:毎月のパート収入から“塾積立”を先取りする
- 半年ごとに費用対効果をチェック:「成績の伸び」と「支払い額」を比較し、継続を判断
- 講習費をボーナス・特別支出扱いにする:定期収入ではなく臨時支出で調整
また、家計簿アプリ(マネーフォワード・Zaimなど)を使えば、教育費の比率を自動で可視化でき、「今月は塾代が多い」「食費を減らせばバランスが取れる」といった判断がしやすくなります。
塾代は「払うことが目的」ではなく、「成果とバランスをとる費用」です。
家計を圧迫しない範囲での“見える化”こそ、教育費を長く続ける秘訣といえます。
家計全体を見直して塾代を確保する3ステップ

収入と支出をクリアにすることで、塾代だけでなく家計全体も改善することが可能です。
ここからは、子供の塾代を確保するための、具体的なステップをお教えします。
まず“教育費の上限”を決める:理想より現実的に設定
塾代が家計を圧迫する一番の原因は、「どこまで教育費をかけるか」が曖昧なまま支払い続けてしまうことです。
“子どものためだから”と際限なく投資してしまうと、パート収入がいくらあっても足りなくなります。
まずは、「教育費の上限」を明確に設定することが第一歩です。
文部科学省の調査によると、子ども一人あたりの年間教育費は、公立中学生で約50万円、高校生では約80万円にのぼります。
この中には塾代が大きく占めるため、「家庭の可処分所得のうち教育費は20%以内」といった現実的な目安を設けることで、無理のない範囲で支出をコントロールできます。
たとえば、年間手取りが300万円なら教育費の上限は60万円。塾代に月3〜4万円以上かかるなら、他の支出を見直す必要があるということです。
「理想」ではなく「家計に合った教育プラン」を立てることで、精神的なプレッシャーも減り、家計全体が安定します。
パート収入と支出を「見える化」してムダを減らす
塾代を確保するためには、「今の家計でどこにお金が流れているか」を正確に把握することが欠かせません。
家計簿をつけているつもりでも、実際は「固定費」「変動費」「教育費」の区分があいまいなケースが多いのです。
ここで効果的なのが、家計の“見える化”。アプリ(マネーフォワード、Zaimなど)を活用すれば、支出の自動分類が可能で、どの項目にどれだけ使っているかが一目でわかります。
特に注目したいのは、以下の3項目です。
- 通信費:格安SIMへの乗り換えで年間3〜5万円の削減
- 保険料:内容を見直すことで月1万円の節約も可能
- 食費・外食費:まとめ買い・冷凍保存で月5,000円の削減
このように、塾代を直接減らすよりも、他の出費を圧縮して教育費に回す方が現実的です。
また、パート収入を「生活費」と「教育費」に明確に分けて管理することで、「今月はいくら塾代に充てられるか」がすぐに判断できます。
家計の流れを見直すだけで、意外と無理なく塾代を確保できる余地が見えてくるのです。
教育費専用口座や積立で、塾代を“計画的に払う”仕組みを作る
塾代を“その場しのぎ”で支払っていると、ボーナス期や講習期に家計が一気に赤字になることがあります。
これを防ぐには、教育費専用口座を作り、積立型の管理に変えるのが効果的です。
たとえば、月2万円を自動振替で教育費口座に移す仕組みを作れば、半年で12万円、1年で24万円が確実に貯まります。
講習費やテキスト代など突発的な支出にも対応でき、精神的な安心感が生まれます。
また、銀行の目的別口座(住信SBI・楽天銀行など)を活用すれば、「塾費用」「進学費用」「習い事費」などを分けて管理でき、用途ごとの残高もひと目で把握することが可能に。
さらに、家計簿と連動させて「使った分だけ自動で補填」するよう設定しておくと、塾代がどのくらいのペースで出ているかを常に把握できます。
このように、塾代を「毎月の支払い」ではなく「積立から計画的に払う」形に変えることで、家計の波を平準化し、塾代による家計圧迫を根本から防ぐことができるのです。
よくある疑問Q&A:塾代とパート収入の両立は本当にできる?
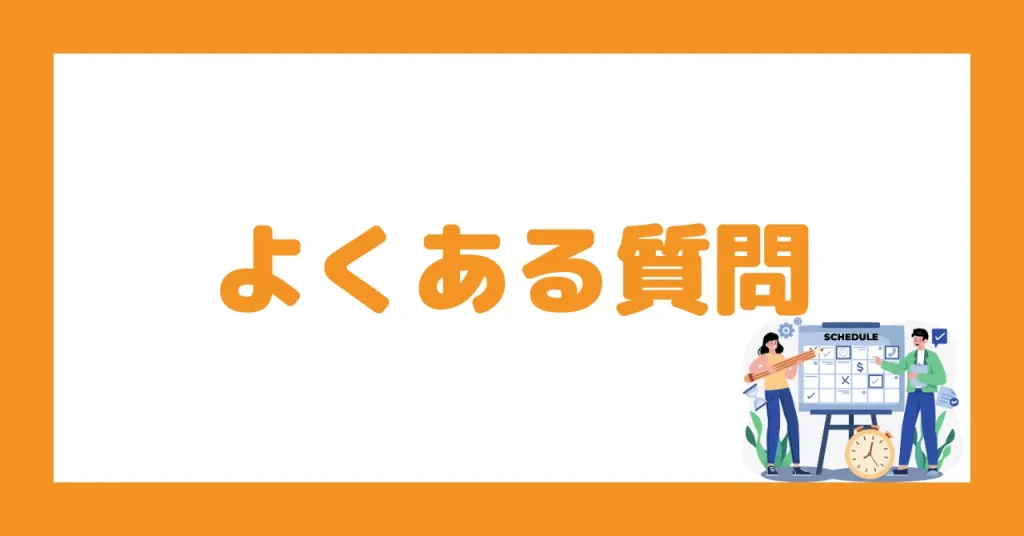
塾代が高くて家計が圧迫される──そんな現実に直面している主婦は少なくありません。
ここでは、主婦のリアルな疑問に答えながら、パート収入で無理なく教育費をやりくりする現実的な方法を紹介します。
「パートを増やせば塾代は払える?」実際の手取りを比較
結論から言うと、「パートを増やすだけでは、塾代の負担が完全に解消するわけではありません」。
なぜなら、働く時間を増やすと扶養控除や社会保険料の壁にぶつかるため、手取りが思ったほど増えないケースが多いからです。
たとえば、時給1,100円で週4日・4時間働く主婦の場合、月収は約7万円。これを「塾の夏期講習費(5〜10万円)」に充てると、ほぼパート収入が消えてしまいます。
そのため、単純に労働時間を増やすよりも、以下のように働く時間と家計支出のバランスを取る工夫が重要です。
- 週3勤務+副収入(ネット販売・在宅ワークなど)でリスク分散
- 「130万円の壁」「扶養範囲内」を意識して手取りを最大化
「時間を増やす」ではなく「効率的に稼ぐ」を意識することが、塾代とパート収入を両立させる第一歩です。
「兄弟がいると塾代が倍になる…」共通費・割引制度を活用する方法
兄弟が多い家庭ほど、「塾代の家計圧迫」は深刻になりやすいです。
しかし実は、塾によって兄弟割引・紹介割引・教材共用制度などを導入しているところも多くあります。
代表的な割引制度としては、
- 2人目以降の授業料が半額〜2割引
- 家族同塾で入会金無料
- 教材費・講習費の共有可能(特に同学年・同コースの場合)
また、近年はオンライン塾や個別指導のサブスク型(定額制)も増えています。
通塾よりも費用を抑えつつ、家庭学習のサポートも得られるため、家計の安定化に役立ちます。
兄弟それぞれに同じだけ費用をかけるのではなく、「一番効果の高い投資先を見極める」意識を持つことが、長期的な教育費コントロールにつながるのです。
「塾代が高いのに成績が伸びない」そんなときの見直しポイント
塾代を払っているのに成果が出ない時に見直すべきは、「子どもの学習スタイルと塾の相性」です。
多くの主婦が「大手塾=安心」と思いがちですが、実際には授業形式や講師の相性、通塾時間のストレスが子どもの集中力を下げているケースもあります。
見直しポイントは以下の通りです。
- 成績アップのために「何を伸ばしたいか(基礎・応用・受験)」を明確化
- 講習費・教材費など“成果に直結しないコスト”を洗い出す
- 家庭学習・通信教材など、成果の出やすい学習スタイルを再検討
「高い塾に通うこと=良い教育」ではありません。
“効果のある投資”に絞る勇気が、主婦の家計を守る最大のポイントです。
「高校・大学まで見据えた教育費の準備」主婦が今からできる対策
今の塾代だけでなく、「この先の教育費」も視野に入れることが大切です。
文部科学省のデータによると、高校から大学までの教育費は合計で約700〜1,000万円。パート収入だけでカバーするのは難しい金額です。
そこで、今から始めたいのが次の3つの準備です。
- 教育費専用口座をつくる
塾代・教材費・講習費などを分離して管理。使途が明確になります。 - つみたてNISAや学資保険を活用
「貯める」だけでなく、「増やす」発想を持つことが重要です。 - 中学・高校進学時に“塾以外の学習法”を選べるよう情報収集
定期的に教育プランを見直すことで、将来の負担を減らせます。
塾代を“今だけの支出”と捉えず、長期的な教育投資の一部として計画的に準備することが、家計の安定につながります。
まとめ:塾代に悩む主婦が“無理なく教育費を守る”ための現実的戦略
子供の塾代に家計を圧迫される主婦は、“子どもの教育を諦めたくないけれど、家計が苦しい”という切実な思いを抱えています。
本記事では、その悩みに寄り添いながら、現実的かつ前向きに塾代と家計を両立させる方法を解説しました。
最後に、今すぐ実践できるポイントを整理してまとめます。
- 上限設定し「現実的な範囲」で塾代予算を決める
- 家計のムダを見直し塾代の余力を確保
- 通塾回数・受講科目・講習費を「成果重視」で選別
- 公的支援・割引制度をフル活用する
- 成果が出ないときは「塾選び」を見直す
- 教育費専用口座で塾代を分離して管理
パート収入と家計のバランスを整えながら、無理のない範囲で子どもの学びを支えることが、何よりも賢い選択です。
あなたの家庭にも、「お金の安心」と「子どもの成長」を両立できる方法は必ずあります。
今日から小さな見直しを積み重ねて、塾代に振り回されない家計を一緒に育てていきましょう。
▼教育費に悩む人の落とし穴をチェック!解決方法はこちらから。