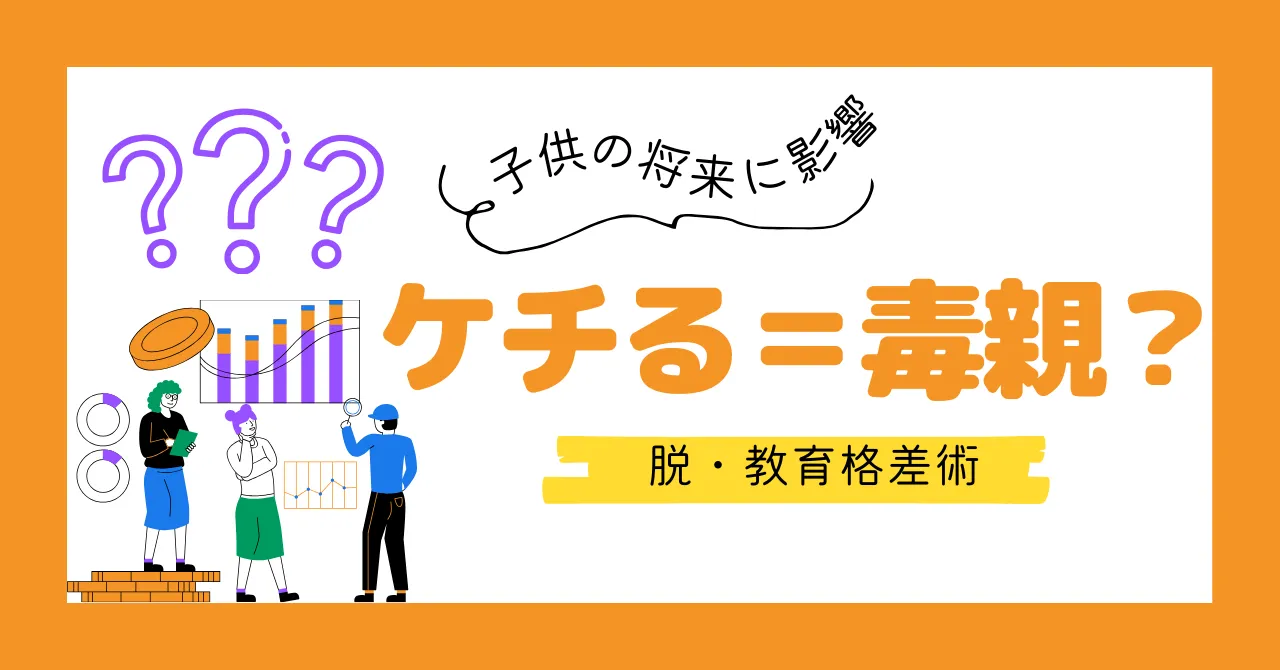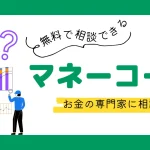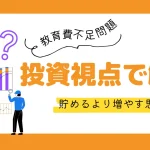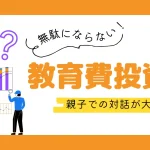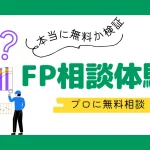「うちの親、教育費をケチっているだけなのかな…」そんな不安を抱えたまま大人になった人は少なくありません。
習い事をやめさせられた理由は本当に“お金”だったのか。塾に行かせてもらえなかった背景には、何があったのか。
そして今あなた自身が親になり、ふと気づく瞬間があります。──“あの時と同じことを、私はしていないだろうか?”
「教育費をケチると子どもの未来はどう変わるのか?」
「親が気づかないまま奪ってしまう「選択肢」とは何なのか?」
「お金の問題だけではなく、親の言葉や態度が子どもの心にどんな影響を残すのか?」
このページではどこよりも深く、リアルで誰も語りたがらない“教育費をケチる親の本当の問題”に切り込みます。
読み終える頃には、あなたの「教育」に対する価値観が必ず変わります。
▼教育費不足に悩む人は、プロに無料相談し解決した実体験を確認してみましょう。
Contents
なぜ“教育費をケチる親”という言い方をするのか?背景と心理
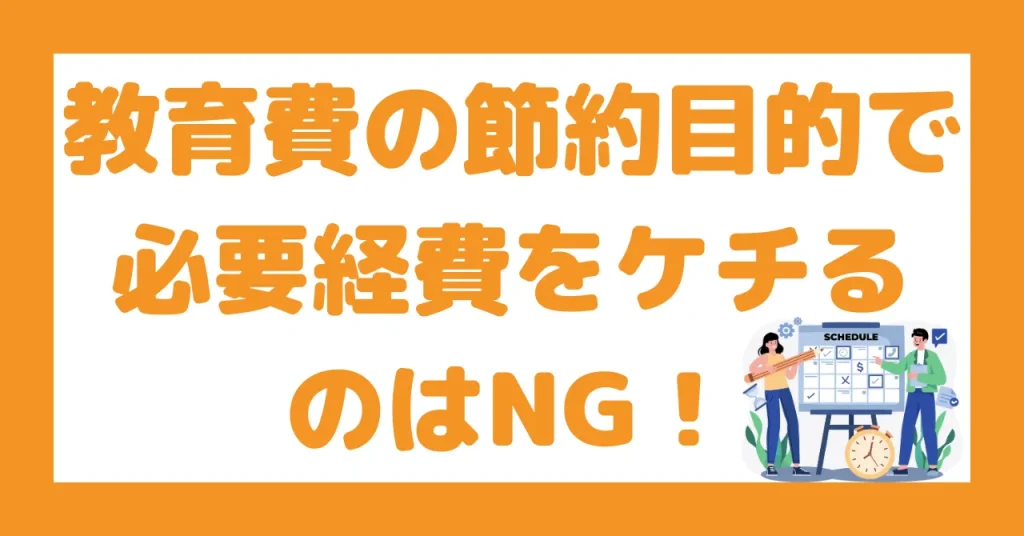
もしかして自分は教育費をケチっているの?そんな悩みを抱える人も、少なくありません。
まずは、”教育費をケチる親”の本当の意味と、なぜ教育費を削ろうとしたいのかを深堀していきます。
“ケチる”という表現の意味と、教育費における使われ方
「ケチる」とは、本来出すべきお金を惜しむ、必要な支出を意図的に減らすというニュアンスを含む言葉です。
単なる節約や倹約とは違い、そこには「気持ちの冷たさ」「余裕がない印象」がまとわりつきます。
教育費においてこの言葉が使われるとき、次のような場面が多く見られます。
- 周囲の家庭が塾や習い事をさせているのに、明確な説明なく断られる
- 進学や学習環境の選択肢を最初から狭められていると感じる
- 「お金がないから無理」と一言で片付けられる
ここで重要なのは、実際にお金があるか・ないかではないという点です。
子ども側は、「話し合いがない」「理由を共有してもらえない」ことに、強い不満や不安を覚えます。
その結果、「教育費をケチられている」という感情的な言葉に変換されてしまうのです。
親が教育費を削ろう・出し渋ろうとする典型的な理由
親が教育費を抑えようとするのには、決して身勝手ではない事情があります。
代表的な理由は、次の通りです。
| ①将来への不安が大きすぎる | 老後資金、住宅ローン、兄弟姉妹の教育費など、「今」よりも「将来の破綻」を恐れるあまり、目の前の教育投資にブレーキをかけてしまうケース。 |
| ②教育費=際限なく膨らむという恐怖 | 塾、習い事、私立進学…。一度出し始めると「どこまでかかるのか分からない」という不安から、最初から抑えようとする親も多い。 |
| ③親自身の成功・失敗体験の影響 | 「自分は塾に行かなくても何とかなった」「高学歴でも苦労している人を見てきた」など、親の人生観が判断基準になっている場合もある。 |
ここで見落とされがちなのが、親は「教育費をケチっている」のではなく、家族全体を守るために必死でバランスを取っているという点です。
しかし、その思いが言語化されないままでは、子どもには伝わりません。
▼足りない教育費は学資保険で補えない!FP無料相談で解決した方法はこちら!
親が“ケチる”と感じる子どもの視点:悩み・不安・影響
子どもが「教育費をケチられている」と感じるとき、心の中では次のような疑問が渦巻いています。

自分は期待されていないのでは?

将来の可能性を最初から諦めさせられているのでは?

お金のせいで、夢を持つ資格すらないのでは?
この感情が積み重なると、単なる学習環境の差にとどまらず、自己肯定感の低下や親への不信感につながることがあります。
特に影響が大きいのは、次の3点です。
| ①挑戦意欲の低下 | 「どうせ無理」「言ってもダメ」という思考がクセになり、チャレンジする前に諦めるようになる。 |
| ②お金=愛情という誤った認識 | 教育費を出してもらえない経験が、「自分は大切にされていない」という認知につながることがある。 |
| ③大人になってからの親子関係への影響 | 進学期のわだかまりは、大人になっても消えず、「あの時もっと話してほしかった」という後悔として残るケースも少なくない。 |
「学力への影響」だけにフォーカスされがちですが、本当に長引くのは心の影響です。
教育費をどう使うか以上に「どう向き合い、どう説明するか」が、子どもの人生観に深く関わってきます。
教育費を出さないことで起こるリスク・本当に困るケース
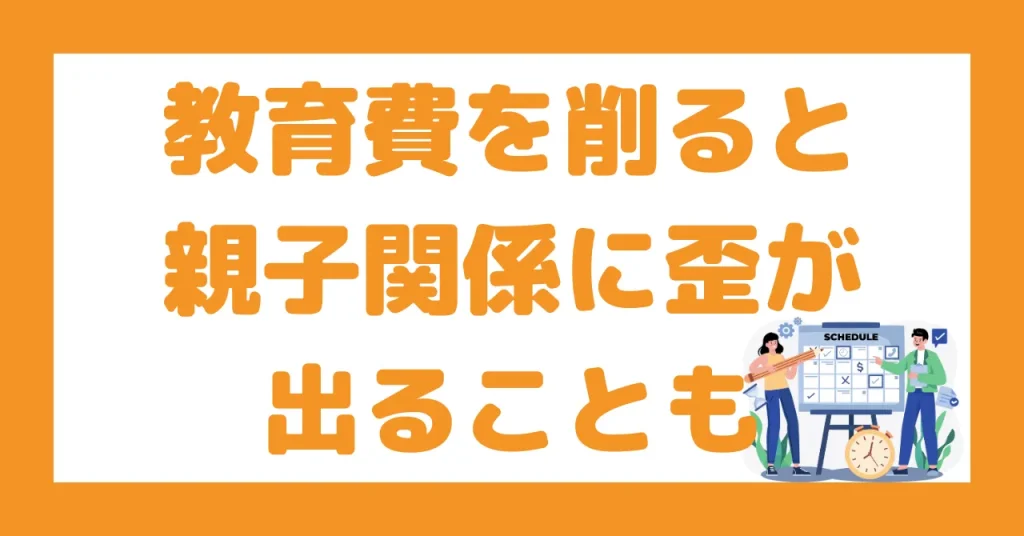
教育費を「ケチる」ことは、単なる節約とは違い、子どもの成長や家庭の土台に長期的な影響を及ぼします。
ここでは、教育費を削ることで起こりうる“本当の意味でのリスク”を、他サイトにはない視点で詳しく解説します。
進学・習い事・受験対策で“出せない”ことが生むギャップ
教育費をケチることで最初に表面化しやすいのが、選択肢の格差です。
たとえば、
- 塾に通えず学校の授業だけで受験に挑む
- 習い事をやりたくても「お金がもったいない」と却下される
- 模試や検定を受けられず自分の実力が測れない
こうした状況が続くと、子どもは「努力不足」ではなく環境差で不利になります。
特に厳しいのは高校・大学受験です。
周囲が当たり前のように塾・オンライン講座・参考書を使う中で、「うちは無理だから」「お金がないから我慢しなさい」と言われ続けると、子どもは挑戦する前から諦める思考を身につけてしまう可能性があります。
「学力差」だけでなく、実際に深刻なのは“選べない人生に慣れてしまう”ことです。
「どうせ無理」「最初から選択肢にない」この思考は、進学後や社会人になってからも影響を残します。
“ケチられた”“出し渋られた”と感じる子どもの心の傷/自己肯定感への影響
教育費をケチることは、親の節約意識とは裏腹に、子どもには愛情の量として受け取られるケースが少なくありません。
- 友達は当たり前にやっているのに自分だけダメ
- 兄弟の中で自分だけ「我慢」を強いられる
- 理由を説明されずただ否定され続ける
この積み重ねが、「自分は大切にされていない」という認識につながります。
特に問題なのは「お金がないから」ではなく、「そんなの意味ない」「無駄だから」という言い方です。
この言葉は、子どもの興味や挑戦そのものを否定された記憶として残ります。
結果として、「自己肯定感が低い」「失敗を極端に恐れる」「お金を使うことに強い罪悪感を持つ」といった大人に成長するケースも珍しくありません。
これは教育費をかけなかった“結果”であり、決して性格の問題ではありません。
家庭内で起こる影響:親子関係・兄弟格差・将来設計
教育費をケチることは、家庭内の空気にも影を落とします。
まず起こりやすいのが、親子関係の溝です。
子どもは思春期以降、「なぜ自分だけ制限されたのか」を冷静に考える傾向に。そのとき納得できる説明がなければ、不信感に変わります。
また、兄弟姉妹がいる家庭では教育費格差が深刻になりがちです。
「上の子にはお金をかけたが、下の子にはかけない」「性別や成績で対応が違う」といった差は、将来まで残るわだかまりになります。
さらに見落とされがちなのが、子どもの将来設計への影響です。
教育費をかけてもらえなかった子ほど、
- 安定より「とにかく早く稼ぐ」選択をする
- 本当はやりたいことを避ける
- 親に頼ることを極端に拒む
という傾向が強くなります。
一見自立しているようで、実は「頼れなかった経験」が根底にあるのです。
“教育費をケチる親”にならないために知っておきたい3つのチェックポイント
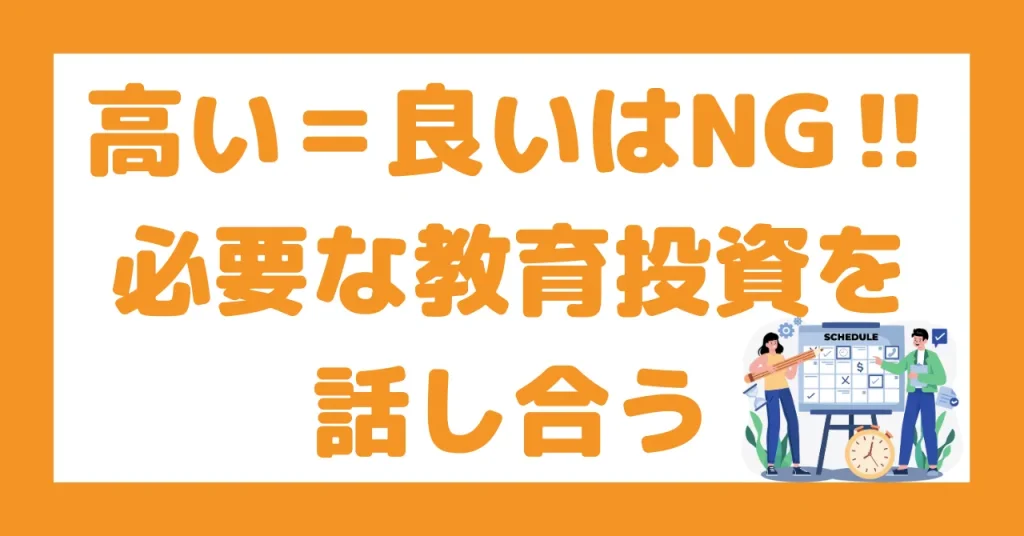
「教育費をケチる親になりたくない」
「でも現実的にお金が足りない…どうすればいい?」
この悩みは、教育費に悩む親の根本的ニーズです。
「教育費は大事です」「投資しましょう」といった“精神論”が中心ですが、
実際に必要な次の3つの視点を解説します。
家計を“教育費込み”で見直す:見落としがちな項目と対策
教育費をケチりたくないのにケチってしまう親は、ほぼ例外なく 「教育費を後回しにした家計管理」 になっている傾向です。
教育費を削る家庭の多くに、共通する支出があります。
- 通信費(スマホ・ネット)
- 固定費(サブスク・保険・車)
- “なんとなく使う”食費・外食費
これらが家計を圧迫し、「教育費を出したくても出せない」を引き起こしています。
まずは、教育費は“余ったら出す”ではなく“最初に確保する枠”として扱うことがポイント。
たとえば、
- 毎月5,000円でも先に教育費として積み立て
- 習い事の月謝を固定費として計上
- 模試や教材費の年間予算を先に組む
これだけで「教育費が出せない」という心理的ストレスは大幅に減ります。
また、保険を払いすぎて教育費が足りない家庭は少なくありません。しかし本来、教育費こそ“子どもの将来を守る最大の保険”。
教育費を削る前に、「本当に削るべきはそこなのか?」を一度立ち止まって考えることが、後悔しない第一歩です。
子どもと“本当に必要な教育投資”を話す:習い事・塾・教材を見極める視点
「周りがやっているから」「やらせないと不安だから」この理由だけで教育費をかけ続けると、家計は苦しくなり、結果的に“ケチる方向”へ振り切れてしまいます。
大切なのは、その教育投資が“誰のため”なのかを明確にすることです。
チェックしたい視点は以下の通りです。
- 子ども自身が興味を持っているか
- 成果や成長を実感できているか
- 目的が「不安の解消」だけになっていないか
特に見落とされがちなのが、子どもと話し合うプロセスです。
親が一方的に「これは必要」「これはムダ」と決めてしまうと、たとえ合理的でも、子どもには「お金を理由に否定された」と感じられることもあるのです。
逆に、「どう思ってる?」「何が一番役に立ってる?」と対話を重ねることで、必要なもの・不要なものが自然と整理されていきます。
教育費をかける=愛情、ではありません。
話し合って選ぶこと自体が、子どもにとっての大きな教育になります。
『出せない』ではなく『出す範囲を見せる』:子どもに納得・理解してもらう工夫
多くの親は、「お金がないからダメ」「高いから無理」という“禁止の言い方”をしがちです。
しかしこの言い方は子どもを納得させず、むしろ不満と不信感を生む最大の原因になります。
子どもは金額そのものより、
- なぜできないのか
- 親はどう考えているのか
- 代わりの選択肢は何か
が分からないと不安になります。
逆に言えば、親が「出せる範囲」を具体的に示せば、子どもは驚くほど納得します。
例えば、こう言い換えるだけで子どもの理解が変わるため、試してみましょう。
| NGな言い方 | 改善案 |
|---|---|
| 「そんな高い塾は無理」 | 「月1万円までなら出せる。そこから一緒に選ぼう」 |
| 「その習い事はお金がかかりすぎる」 | 「2つは難しいけど、1つなら継続できるよ」 |
| 「ゲームばかりして!塾に行きなさい」 | 「月に払えるのは○円。自学の計画も含めて一緒に決めよう」 |
これにより、子どもは「自分も家計の一部を理解している」という感覚を持ち、お金に対する不安や不満が強く減ります。
親子が“同じ情報”を持つことで、
- 途中で文句が出ない
- 親子の合意形成ができる
- 無駄な出費が減る
- 子どもが主体的に選べるようになる
というメリットが生まれます。
「出すか/出さないか」の対立を避けられることが、最大の効果です。
▼教育費の“必要か無駄か”を判断する基準はこちらで詳しく紹介しています。
実践!教育費を“賢く出す”ためのステップ&制度活用

教育費を「ケチる」状態から抜け出すためには、感情論ではなく、“数字”と“制度”を味方につけることが決定的に重要です。
ここでは、今日からできる「賢い教育費の出し方」を、ステップ形式でわかりやすく紹介します。
支出優先順位をつける:教育費・生活費・貯蓄のバランス
教育費をケチらないための第一歩は、「家計の中で教育費をどこに置くか」を明確にすることです。
多くの家庭でありがちな問題は、以下の3つ。
- 教育費の位置づけが曖昧
- 生活費が膨らみ、教育費は「余ったら出すもの」
- 貯蓄を守りすぎて、必要な投資ができない
教育費は本来「余りで払う費用」ではなく、「将来の収入につながる投資」。
そのため、まずは家計を以下の3カテゴリに分類して考えるのが有効です。
| カテゴリ | 分類ポイント |
|---|---|
| ① 固定生活費 (家賃・食費・光熱費など) | ・見直しやすいのは通信費、保険料、サブスク ・ここの削減は教育費UPにつながりやすい |
| ② 教育費 (塾・教材・受験・学校活動など) | ・「必要なもの」と「感情で選んだもの」を分けて整理 ・受験や習い事は“目的から逆算”して費用対効果を判断 |
| ③ 将来の貯蓄・投資 (NISA・預金など) | ・“貯めすぎて教育費が出せない”家庭も多い ・貯蓄と教育費のバランスを可視化。 |
優先順位を明確にすることは教育費を作るだけでなく、家計全体のコストカットにもつながるのです。
▼自分で家計管理が苦手な人は、お金のプロに相談するのがおすすめ!
公的制度・助成金・奨学金のチェックリスト
「お金がないから教育費を削るしかない…」そう思い込んでいる家庭は多いですが、実は教育分野は国の支援がかなり手厚いのが現実です。
ここでは、“使える可能性が高い順”に「すぐ使える制度一覧」をまとめます。
| 制度 | 内容 |
|---|---|
| ① 高校無償化 (高等学校等就学支援金) | ・所得制限内なら授業料が実質ゼロに |
| ② 私立高校補助金 (自治体) | ・自治体独自の追加支援あり ・条件を見落とす家庭が多い |
| ③児童手当 (高校卒業まで) | ・塾代・教材費として活用可能 ・使い道は自由 |
| ④大学の給付型奨学金 (JASSO) | ・返済不要 ・特に家計が厳しい世帯は優先度が高い |
| ⑤授業料減免制度 (国公立・私立大学) | ・大学によって制度が異なる ・対象になれば負担は大幅軽減 |
| ⑥教育ローン (日本政策金融公庫) | ・民間より低金利 ・教育に特化した借入 |
また、見落としがちなのが以下のような制度です。
- 学習支援の自治体助成
- 通信教育費の補助
- 兄弟の人数で補助が増える制度
- 寮費・通学費の補助
制度を使って教育費を“作る”視点を持てば、ケチらなくてもさまざまな選択肢を残せます。
“教育費をケチらない”ための家計モデル公開:月額/年額目安
「どのくらい教育費をかければ“ケチっている”状態から抜け出せるのか?」この問いに明確に答えるため、具体的な家計モデルを提示します。
まずは、一般的な収入家庭の教育費の目安です。
モデル①:世帯年収500万円
- 幼児〜小学生:月1.5万〜2.5万円(習い事+学校関連)
- 中学生:月2万〜4万円(塾・部活・教材)
- 高校生:月1.5万〜3万円(学校活動+模試)
- 大学進学準備:年間10万〜50万円(受験・講座・旅費)
平均的に、「月3万円の教育費」が基準。月1万円以下だと、“必要な教育投資ができない可能性”が高いです。
次は、慎重な家計でも教育費を確保したい場合の目安を確認します。
モデル②:世帯年収300〜400万円
- 幼児〜小学生:月1.5万〜2.5万円(習い事+学校関連)
- 中学生:月2万〜4万円(塾・部活・教材)
- 高校生:月1.5万〜3万円(学校活動+模試)
- 大学進学準備:年間10万〜50万円(受験・講座・旅費)
ポイントは、「少額でも継続して投資」を行うこと。長期的な視点を持つことで、必要な教育費を確保できます。
最後は、比較的経済的余裕がある共働き世帯です。
モデル③:世帯年収700〜900万円
- 月4万〜6万円(中学〜高校の塾が中心)
- 大学費用の積立:月2万円〜3万円
この層は「貯金不安」から、“教育費をケチる必要がないのにケチってしまう”ケースが多く見られます。
しかし、受験期の教材費・講座費を削ると後で後悔する可能性が高いです。
教育費は「出せるかどうか」で悩むものではありません。
「どう出すのが最も子どもにとってプラスか」を軸に考えることで、“ケチってしまう親”から“賢く投資できる親”へと変わっていくことができます。
親が“ケチる”という判断をしないために、子どもに伝えたい言葉と言葉遣い
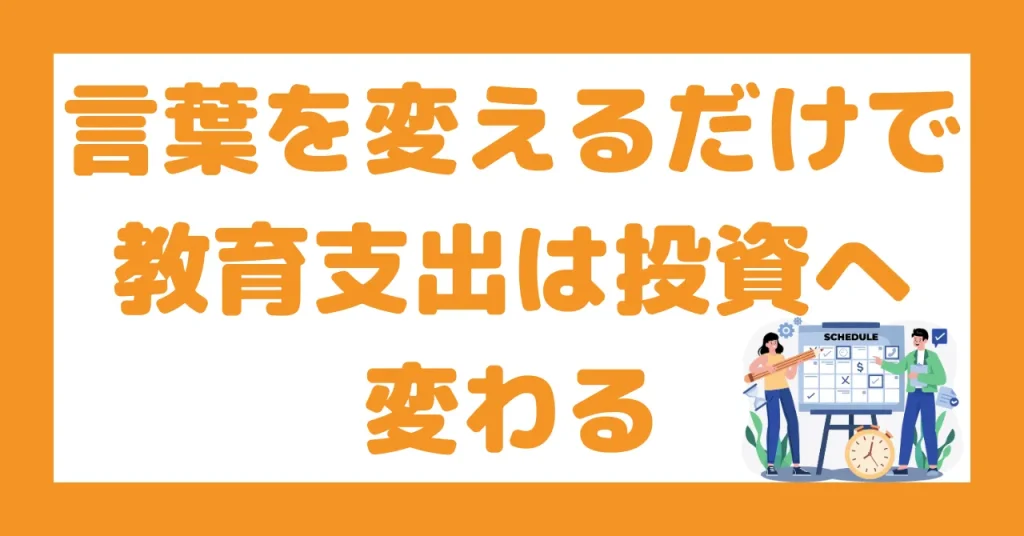
「教育費をケチる親になりたくない」。しかし現実には、家計の余裕・親自身の価値観・子どもへの期待と不安が入り混じり、“お金が出せない・出したくない”と感じてしまう瞬間があります。
そこで重要になるのが 「言葉の使い方」 です。
ここでは、“コミュニケーションの観点から見た教育費の伝え方”を徹底解説します。
伝え方:「投資」として教育を捉える言葉の使い方
教育費は、単なる「支出」ではありません。
子どもの未来の収入・選択肢・人生満足度に直結する“投資”です。
しかし、多くの家庭では、教育の話をする際に以下のような言葉を使っています。

お金がもったいない

そんなのに払う価値はあるの?

うちは余裕がないから無理
これらの言葉は、子どもの心に

自分には価値がないのかな

親に負担をかけているのでは

挑戦してはいけないのか
といった深刻な誤解を生む原因になります。
そこでおすすめなのが、以下のように“投資の視点”を言語化することです。
教育費を前向きに伝えるための言葉
- 「あなたの未来の選択肢が広がる投資だよ」
- 「今のうちに経験を積めば、のちの人生が楽になるよ」
- 「必要なことにはちゃんとお金を使うつもりだよ」
- 「長い目で見て、これはあなたにプラスになると思う」
これらの表現は、子どもに「自分は応援されている」と感じさせる効果があります。
さらに、判断が難しい時はこう伝えるのが効果的です。

これが本当に必要なのか、一緒に考えよう

一度整理して、優先順位を決めよう
“参加型”の対話を意識すると、子どもは「ケチられている」ではなく「話し合って決めている」と認識するようになります。
NGワード/OKワード一覧:子どもが“出してもらって当たり前”と感じないために
教育費をケチらないことと、子どもに「なんでも出してもらえる」と誤解させることは別問題です。
そのためここでは、“依存を防ぎつつ、親子共に納得できるコミュニケーション” のための言葉表現をまとめます。
まずは、子どもが誤解しやすい危険な表現を確認してみましょう。
| NGワード | 理由 |
|---|---|
| 「お金がないから無理」 | 子どもは「家庭は貧しい」と思い込み、自信や希望を失う。 |
| 「そんなものに使うお金はない」 | 「親にとって自分は価値がない」と感じる。 |
| 「兄弟(姉妹)がいるから無理」 | 兄弟間の格差感・不公平感を生む。 |
| 「どうせ続かないでしょ」 | 子どもの挑戦心を折る。 |
逆に、「子どもが責任感を持ちながら前向きになれる表現」を知っておくことも大切です。
| OKワード | 理由 |
|---|---|
| 「できる範囲で一緒に考えよう」 | 家族として協力している感覚が生まれる。 |
| 「続けたい気持ちがあるなら応援したい」 | 子どもが自分の意思を持てる。 |
| 「この費用がどれだけ必要なのか、一緒に整理しよう」 | 金銭感覚が育つ。 |
| 「やりたい理由を教えてくれる?」 | 子ども自身の目的意識が明確になり、親も判断しやすい。 |
“出さない理由”ではなく、“どう選ぶか”に焦点を当てた言葉を使うのが鍵。
これにより、子どもは「親がケチだから出してくれない」のではなく、「一緒に考えてくれる家族」という印象を持ち、自尊心が保たれます。
実例:出し渋りから話し合いに切り替えた家庭のリアルストーリー
最後に、実際にあった“教育費をケチってしまいかけた家庭”が、言い方を変えることで親子関係まで改善したリアルエピソードを紹介します。
ケース:中2の娘が「塾を増やしたい」と言い出した家庭
母親は思わずこう言いかけました。

そんなの無理。お金がかかりすぎるから。
しかし、ふと“言い方を変えよう”と思い直し、こう伝えたのです。

どうして増やしたいと思ったのか、教えてくれる?
娘は、

高校で行きたいところが見つかった。数学をもっと伸ばしたい。
と話し始めました。
そこで母親はさらにこう続けました。

応援したい気持ちはあるよ。ただ、家計もあるから一緒に検討しよう。

体験授業に行ってみて、合うなら考えようか?
結果、娘は体験授業を受け、その塾が本当に良いと納得。母親は助成制度も調べ、無理なく通える範囲で契約することに。
この家庭では、以下のような変化がありました。
- 母親は「ケチってしまった」と後悔せずに判断できた
- 娘は「親に反対された」ではなく「応援してくれた」と感じた
- 家計もムリがなく負担感が減った
- 親子の会話が増え、進路の話がしやすくなった
多くの家庭で起こる“教育費ブロック”は、実 お金の問題の前に「言葉の問題」 が横たわっています。
まとめ:親の言葉が、教育費の“ケチりスパイラル”を断ち切る
教育費は単なる出費ではなく、「子どもの人生の選択肢を広げるための投資」です。
それでも現実には、親の価値観や将来への不安・家計の余裕・知識不足といった理由から、本来必要な教育投資が後回しにされてしまうケースは少なくありません。
本記事をまとめると、
- 教育費=出費ではなく未来への投資
- 教育費をケチると学力・経験・自己肯定感に悪影響が出る
- お金がないから何もしないは最も危険
- 習い事は興味や成長するものを選ぶ
- 補助金・自治体制度・無料教材・オンライン学習を賢く活用
- 家計の優先順位見直しで教育費不足は解消できる
教育費を節約しすぎると、子どもの学力や経験の幅が狭くなるのはもちろん、自己肯定感の低下や「自分は大切にされていない」という誤った認識を生む可能性もあります。
だからといって、無理をして高額な習い事に通わせる必要はありません。本当に大切なのは、子どもの興味や可能性を最初から閉ざさないことです。
教育は“長期的に最もリターンの大きい投資”。今日からできる小さな一歩で、子どもの未来は確実に変わっていきます。
▼教育費は投資視点で解決!大学進学まで700万貯める方法はこちら!